
ステレオ録音の音源をモノラル化すると高域が引っ込んで聞こえる現象について、生成AI(Perplexity)にまとめてもらった。
ステレオで聴いているときはシンバルがキラキラしているのに、モノラルに切り替えた途端、急におとなしく感じることがあります。
EQをいじったわけでもないのに「高域がどこかへ行ってしまった」ように聞こえるこの現象の裏には、「位相キャンセレーション」という少しマニアックな仕組みが潜んでいます。^10
ステレオをモノラルにするときにしていること
ステレオ信号をモノラルにするときには、左(L)と右(R)の信号を足し合わせて、1本の信号として扱うやり方がよく使われます(これを L+R と書くことにします)。^12
ところが、実際にモノラルにしてみると、「高域だけが痩せたように聞こえる」「シンバルの存在感が薄くなる」といったことが起きる場合があります。これは単なる音量の変化ではなく、左右の信号の“重なり方”に理由があります。^14
位相キャンセレーションとは何か
波の世界では、「同じ形の波が同じ向きで重なると大きくなり、逆向きで重なると打ち消し合う」という性質があります。
オーディオで言う位相キャンセレーション(phase cancellation)は、この「打ち消し合い」が音声信号の中で起きる現象のことです。^16
ステレオでは、広がりや奥行きを作るために、左右の信号のタイミングや山谷の位置(位相)をわざと少しずらしている場合があります。
リバーブやコーラス、ステレオディレイなどの広がり系エフェクトは、左右の違いを積極的に作り出すことで空間感を演出していますし、マイク録音でもマイク位置の違いによって左右でわずかなズレが必ず生じます。^11
この「少しずれた左右」を L+R で足し合わせると、ある周波数では片方が山のときにもう片方が谷になり、互いを部分的に打ち消してしまうことがあります。
その結果、特定の帯域だけがスッと引っ込み、「シンバルや高域の空気感が薄くなった」「音が細くなった」といった聴こえ方になるわけです。^18
phase cancellation という言葉について
このような「位相のズレによる打ち消し」を、英語では一般的に phase cancellation と呼びます。録音・ミックス・マスタリング向けの解説記事やチュートリアルでは、ごく当たり前の用語として登場します。^19^16
日本語では、対応する言い方がいくつかあり、表記に揺れがあります。
- フェイズ・キャンセレーション
- 位相キャンセル
- 位相の打ち消し/位相による干渉
といった形で紹介されることが多く、どれか一つに完全に統一されているわけではありません。^20^18
概念自体は、録音やPA、DTMなどの現場では広く知られていますが、一般的なオーディオファン向けの言葉としては、まだそこまで浸透していない段階と言えそうです。
初期ステレオ録音で目立ちやすい理由
1960年前後のステレオ初期の録音を聴くと、ドラムとベースが片チャンネル、コーラスやピアノが反対側、といった極端なパンニングに出会うことがあります。
「ステレオになった」というインパクトを示す目的もあり、左右を大きく分けたミックスが多く作られていた時代です。^22
こうした録音をモノラルにまとめると、いくつかの要因が重なって、位相キャンセレーションが目立ちやすくなります。
- マイクの距離や配置の違いによる、左右の時間差・位相差
- 部屋鳴りやエコー室の反射が、左右で違う形で混ざっている
- 楽器そのものが左右でまったく違う役割を担っている(ハードパン)
これらを一気に L+R で足し合わせたとき、特定の楽器や帯域が「予想以上に痩せる」ことがあります。
たとえば、シンバルの高域成分や部屋の残響だけが妙に引っ込んだり、ある楽器の存在感だけが唐突に薄くなったりする、といった具合です。^15^25
極端なパンによる違和感を軽減しようとしてモノラル合成を試すと、今度は位相キャンセレーションのせいで別の種類の違和感が出てくる、というジレンマもここにあります。
一方で、片チャンネルだけを両耳に送れば位相キャンセレーション自体は避けられますが、反対側にいた楽器がほとんど聞こえなくなってしまうため、これも根本的な解決にはなりません。
どこまで気にするか、どう付き合うか
では、位相キャンセレーションはどの程度、気にするべきなのでしょうか。
現代の制作では、「最終的な再生環境」を見据えてバランスを取る、というのが現実的な落としどころになっています。
- スマホの内蔵スピーカーや店内BGM、ラジオ、テレビの小型スピーカーなど、モノラルあるいはモノラルに近い環境を想定する場合
→ ミックスの途中で意識的にモノラルチェックを行い、「モノにしても致命的に痩せないか」を確認する。^24^15 - ヘッドフォンやちゃんとしたステレオシステムでの再生を前提に、「広がりや包まれ感」を優先したい作品の場合
→ ある程度のモノ互換性低下は織り込み済みとし、ステレオでの心地よさを優先する。^27
重要なのは、「モノラルにすると高域が痩せる」「古いステレオ録音で一部の楽器だけ妙に引っ込む」といった現象を、“なんとなく不思議なこと”で終わらせず、
「左右の信号を L+R で足したときに、位相の違いが一部を打ち消している」という構造として理解しておくことだと思います。^10^18
ステレオの広がりと、モノラルでの壊れにくさは、位相キャンセレーションを挟んだ綱引きのような関係にあります。
その綱をどちら側にどれだけ引くかは、用途や美学によって変わりますが、一度この仕組みを押さえてしまえば、「なぜそう聞こえるのか」を自分の言葉で説明できるようになり、録音や再生の試行錯誤がずっと楽しくなるはずです。
コラム:アナログレコードの45/45ステレオ方式と位相の関係
アナログレコードのステレオ録音は、1957年にウエストレックス社が開発した「45/45方式」が主流です。この方式では、溝の左右の壁がそれぞれ45度傾いた形で刻まれ、針先が横方向(ラテラル)と縦方向(バーチカル)の合成された動きを捉えます。^2
幾何学的に見ると、横方向の動きは L+R(モノ成分)、縦方向の動きは L−R(左右差成分)に相当します。再生側のステレオカートリッジには、45度傾いた方向に感度を持つコイルが2つ入っていて、この合成運動を機械的にベクトル分解して、左チャンネル L と右チャンネル R を取り出します。^3
数式で書くと、和を \(M = L + R\)、差を \(S = L – R\) としたとき、
$$
L = \frac{M + S}{2}, \quad R = \frac{M – S}{2}
$$
という関係になり、理想的には完全に可逆な変換です。つまり、L+R / L−R に一度変えても、両方を持っていれば元の L/R に位相関係も含めて戻せます。^29
ここで位相キャンセレーションがどう絡むかと言えば、L+R を作る段階で、L と R の間に逆相成分があれば M 側で「消えたように見えます」が、そのエネルギーは S 側に移っているだけです。L+R と L−R の両方をセットで扱う限り、復元時には元の位相が失われません。^30
ただし、現実のレコード制作では、カッティング時に低域の L−R 成分を制限する「低域モノ化」などの処理が入ります。これは溝の安定性を保つためですが、結果としてステレオ感が少し抑えられ、位相の自由度が狭まる要因になります。
また、カートリッジのコイル配置や機械精度の限界から、左右の分離は20〜30dB程度が実用値で、理想的な電気式デコードよりはクロストーク(相互干渉)が残ります。この「少しのずれ」が、レコード特有の柔らかいステレオ感や、過度にシャープでない高域のニュアンスを生んでいる可能性があります。^31^33
45/45方式は、機械的なベクトル分解で L/R を実現する美しい設計ですが、物理的な制約が位相キャンセレーションの「味」を自然に織り交ぜている好例です。現代のデジタルミックスと比べてみると、位相の扱いの違いがより鮮明に浮かび上がります。^34^36
^1^5^7^9
⁂

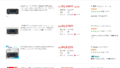

コメント